日曜の朝、いつものように部活へ行くためこの1年ほどで大分着慣れたカッターシャツに袖を通す。ネクタイもきっちりと締めてから居間へと降りると、それに気付いた母が食卓を整える手を止めて俺へと振り返った。
いつものようにおはようと告げれば、「おはよう蓮二」と何だか嬉しそうに笑う。俺が訝しくげに眉を寄せても、機嫌の良さそうな母の表情は崩れなかった。
「今年も届いてるわよ。ちゃんから」
その言葉と共に渡された小包を見て、そういうことかと納得する。母は初めてに会った時から、「礼儀正しくて良い子ね」とのことをいたく気に入っていた。どうやら自分が気に入っている人間から、息子がバレンタインのチョコレートを貰うことができているという事実は母親としてはとても喜ばしいことらしい。「蓮二のお嫁さんになってくれないかしら」という母の言は、既にバレンタインの恒例のようなものだ。
バリ、と簡素なつくりの箱を開き、その中から現れた綺麗なラッピングボックスをそっと手に取る。同封された薄緑のカードを片手で開けば、自然と笑みが零れた。
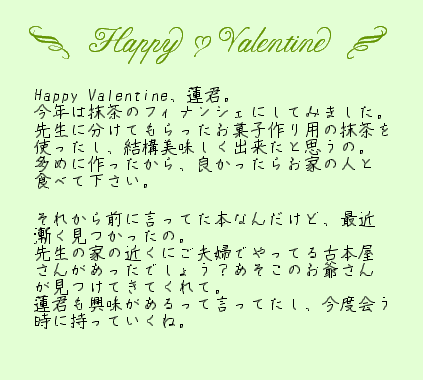
Happy
Valentine、と言いつつもバレンタインなんて行事をあまり気にしていそうにないその内容に、らしいと笑みが深くなる。
「母さん、お家の人にもどうぞ、だそうだ」
「あら、いいの?ちょっと大きめだったからそうかとは思ったんだけど、毎年悪いわねぇ」
そうは言いつつもやはり嬉しそうに笑う母に包みを託して、ポケットから携帯を取り出す。電話帳からの番号を呼び出すと、そのまま通話ボタンを押した。日曜の朝だということを考えれば少し早すぎる時間だが、の起床時間に曜日は関係ない。
『……蓮君?おはよう、どうかしたの?』
「ああ、おはよう。バレンタインのチョコレート……というより、菓子か。とにかく無事こちらに届いたからな、礼をと思って。ありがとう、母も喜んでいたぞ」
『あ、そうなの?わざわざありがとう。ごめんね、あんまりバレンタインらしくはないんだけど』
「いいじゃないか、バレンタインらしさなんて。こちらの好みに合わせてくれたんだろう?嬉しいよ、家族も抹茶は好きだしな」
『そっか、良かった。あ、そうだ、あの本のことなんだけどね……』
そんな風に暫く会話をした後でふと目を向けた食卓はすっかり朝食の準備が終わっていて、咄嗟に目をやった時計が指し示している時間に少しの焦りが生まれる。まずい、少し時間を割き過ぎた。
「、すまない。俺から掛けておいて悪いんだが、そろそろ時間がなくなってきた」
『え、あっ、そっか。立海は今日も練習なんだよね。ごめんね、話し込んじゃって』
「いや、それは構わない。俺の電話をするタイミングが悪かったんだ」
『ううん、そんなこと。練習、頑張ってね』
「ああ、ありがとう。じゃあな」
ピッと電話を切って食卓につくと、向かいに座った母が俺を眺めながら「ちゃん、蓮二のお嫁さんになってくれないかしらねぇ」という例の台詞を口にした。
「それとも、うちの子じゃ駄目かしら。小さい頃から綺麗な子だったもの、きっとモテるわよね……」
「母さん、何度も言うようだが、余計なお世話だ」
はいはい、とつまらなさそうに呟いて箸を取る母を尻目に、傍らに置いたカードを再びそっと開く。繰り返す手紙のやりとりで既に見慣れたものとなった、の文字。流れるようなその文字が宅配便の送り状に書かれたそれよりも幾分寛いでいることを知っているのは、俺だけで問題ないだろう。
同封カードに書かれた文字